近年、「肌色」という言葉は言い換えられ、文具からも姿を消しつつあります。

私が子どもの頃に使っていた色鉛筆やクレヨンには、「肌色」と書かれているのが普通でした。
その時は、「肌の色」という解釈をすることなく、この色が「肌色」だと認識していました。
それは、私が幼くて、人種によって肌の色が多様であることを知らなかったからだと思います。
この記事では、現代における「肌色」の言い換え例、言葉の歴史、そして言い換えが行われた理由などについて紹介します。
目次
肌色の言い換えはいつから?そもそもいつから肌色と呼ばれていた?
肌色の大きな変化の一例として、大手文具メーカーが「肌色」の表現を廃止したことがあります。
ぺんてるは1999年に、三菱鉛筆・サクラクレパス・トンボ鉛筆の3社は2000年に「肌色」の言い換えを発表しました。
そしてトンボ鉛筆、三菱鉛筆、サクラクレパスの三社は「はだいろ」の名称を「うすだいだい」に変更することを決定しました。
この決定を契機に、日本全体で「はだいろ」の名称を廃止する動きが加速し、2005年から2006年にかけて全てのクレヨンからこの名称が消えました。
また、この問題については経済産業省のJIS改正案作成委員会でも議論されました。
もともと「肌色」という言葉は、日本人の肌の色を表す淡いオレンジ色として使われていました。
この言葉は、江戸時代以前、仏教が広まる前の日本で「宍色(ししいろ)」として知られていました。
宍とは、食用とされていた動物の肉を指す言葉です。
しかし、徳川綱吉の時代に始まった「生類憐れみの令」により、「宍色」という言葉は避けられるようになり、「肌色」という表現が広まりました。
時代が進み、大正時代になると自由画教育が導入され、絵具や色鉛筆の需要が増加しました。
昭和初期には、子どもたちが人物の顔を描く際に一般的に使用されるようになったと言われています。
最近では、肌色の表現が更新され、次の3つの言葉が頻繁に使用されています。
うすだいだい
この言葉は「薄い橙色」という意味で、日本独特の色彩表現です。
温かみのある明るいオレンジ色を穏やかに表現しています。
ペールオレンジ
これは「淡いオレンジ色」を指す言葉で、英語の「pale orange」に由来します。
柔らかく明るいオレンジ色を意味します。
ベージュ
ベージュはフランス語から来た色名で、淡い黄色や茶色のニュアンスを含んだ色を指します。
日常生活でも馴染みやすい色です。
これらの言葉は、従来の「肌色」の代わりに使われ、肌の色の多様性を反映した現代的な表現として広く受け入れられています。
それぞれの言葉について詳しく説明します。
うすだいだい
「うすだいだい」という色は、日本の伝統的な色のひとつです。
この名前は、ダイダイという果物に由来しています。
ダイダイオレンジはその名の通りオレンジ色ですが、特に明るく鮮やかな色合いを持っています。
「うすだいだい」は、このダイダイオレンジよりも薄い色味で、優しいオレンジ色を表現しています。
生き生きとしたオレンジ色に、黄色と赤のバランスが絶妙に混ざり合っているのが特徴です。
この色は、かつて「肌色」と呼ばれていた色の新しい名称として選ばれました。
この変更は、多様な肌の色を持つ人々を尊重し、一つの色に固定せず、より広い意味を持つ色表現へと変わることを意図しています。
明るくて温かみのある「うすだいだい」は、現代の日本での新しい肌色の代表として認識されています。
ペールオレンジ
「ペールオレンジ」とは、薄くて明るいオレンジ色を指す言葉です。
英語の「pale」という単語には「薄い」や「淡い」という意味があります。
この言葉を使って、オレンジ色の一種を表現しています。
ペールオレンジは、色味として「淡い橙色」に非常に近いと言えます。
そのため、両者はほぼ同じ色合いを持っていると考えられます。
ペールオレンジは、その柔らかくて温かみのある色合いから、多くの場面で使用されています。
ベージュ
「ベージュ」という色は、肌色の代わりとしてよく使われる色です。
この色名はフランス語に由来し、優しい黄色や茶色のトーンを含んでいます。
日本工業規格では、ベージュは淡くて少し赤みを帯びた灰色の黄色として定義されています。
この色は、化粧品の世界では特に一般的で、ライトベージュやピンクベージュなど様々なバリエーションがあります。
日常生活では、淡い橙色やペールオレンジといった色名よりも、ベージュという言葉をよく耳にすることでしょう。
ベージュは非常に身近な色で、肌色を表現する際に自然に溶け込み、違和感なく使用できる色です。
肌色が呼ばれなくなったのはいつからでしょうか?
日本では長い間、「はだ色」という表現が一般的でしたが、近年になってこの言葉の使用に対する見方が変わってきました。
多様な民族が存在する日本で、特定の色を「はだ色」とすることが差別的な意味を含むという指摘が出てきたのです。
特に教育の場では、「はだ色」という言葉の使用に対する抵抗が強まりました。
これを受けて、2000年頃に大手のクレヨンメーカーが製品名を変更しました。
例えば、ぺんてるは「ペールオレンジ」に、サクラクレパスは「うすだいだい」に改名しています。
こうして、「はだ色」という名前は、色鉛筆や絵の具などの画材から徐々に姿を消していきました。
この変化は、社会の意識の変化とともに、言葉の使い方にも配慮するという現代の風潮を反映しています。
まとめ
「はだ色」という表現は徐々に変わりつつあり、それに応じて商品のラベルや色の名称も更新されています。
しかし、日本における肌の色の多様性や人種の違いに対する認識はまだ十分とは言えません。
決して「肌色」という言葉を使ってはいけないわけではなく、場合に応じて会話の中で日常的に使われることもあると思います。
それでも、私たちが重視すべきは、肌の色が人それぞれ異なるという事実です。
この多様性を正しく理解し、尊重する姿勢は、これからの時代において非常に重要です。
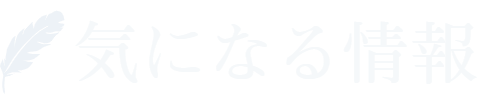



コメント