絵を描くときや工作をする際に、肌色を使いたくなることがありますよね。

でも、もし手元に肌色の絵の具がなかったり、持っている絵の具が思っている色と違ったらどうしますか?
今回は、驚くほど簡単にできる肌色の絵の具の作り方をご紹介します。
微妙な色の調整方法も併せてお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
絵具と色鉛筆では肌の色を表現する方法が異なるため、色鉛筆での色の作り方についても説明しています。
ところで、以前は「肌色」と呼ばれていた色ですが、今では違う名称が使われています。
どうして名前が変わったのか、そして現在の呼び方についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
絵の具で肌の色を作るには、3色で十分です!
最近、「肌色」という絵の具が販売されていないことをご存知ですか?
肌の色は人それぞれで、特に人種によって大きく異なります。
最近では、人種の多様性や個性を
尊重する動きが進んでいるため、
「肌色」という表現は
適切ではないと考えられるようになりました。
この表現が変わり始めたのは
2000年頃からです。
クレヨンや色鉛筆などのメーカー、
例えばぺんてるや三菱鉛筆などでは、
「肌色」を「ペールオレンジ」や「うすだいだい」に
変更しました。
もし、「肌色」の絵の具を探していて
見つからない場合は、
色の名前に注意してみてください。
なお、この記事では分かりやすさを
優先して、引き続き「肌色」という表現を
使用させていただきます。
絵の具で肌の色を作る方法について
さて、今回は絵の具を使って肌色を作る方法を紹介します。
肌色は、赤、黄、白の3色を組み合わせることで簡単に作れます。
まず、赤と黄を混ぜてオレンジ色を作り、そこに白を加えて色の濃淡を調整します。一般的な配合は、「赤1:黄1:白4」です。
日本人の肌には黄色が含まれているため、黄色は欠かせません。
赤を少量加えることで、健康的な血色を再現します。
さらに白を混ぜることで、肌の明るさを引き出します。
まずは基本の配合で肌色を作り、自分のイメージに合わせて「もう少し黄色が欲しい」「ピンクに近づけたい」など、少しずつ絵の具を加えて調整してみましょう。
肌色の絵の具を自分好みに調整しよう!
肌色を作るための色の組み合わせには、他にもいくつかの方法があります。
実際、これから紹介する組み合わせの方が、より日本人の肌の色に近づけやすいのです。
先ほど「赤・黄・白」の組み合わせを最初に紹介した理由は、子どもや絵画初心者でも簡単に肌色を調整できるからでした。
「もっとリアルな肌色を追求したい!細かい調整をしたい!」という方は、これから紹介する2つの組み合わせをぜひ試してみてください。
①「茶・白・赤」
色黒や浅黒い肌を表現したい場合は、茶色を用います。
まず、茶色と白を混ぜて濃い肌色のベースを作ります。
次に、赤を加えることで血色感を加え、よりリアルで立体的な肌色が完成します。
濃い肌色を作る際には白が役立ちます。
ただし、「色黒な肌にしたいけれど、もう少し明るくしたり透明感を持たせたりしたい」という場合には、水で調整すると上手くいくことが多いです。
「肌色」と一言で言っても、人それぞれ肌の色は異なります。
さまざまな絵の具の混ぜ方を知ることで、多様な肌色を表現することができるようになります。
ぜひ、いろいろな組み合わせを試して、自分の理想の肌色を作り出してください。
②「赤・黄・青」
人間の肌には青みが含まれています。
これは、青色の静脈が肌の下を通っているためです。
パーソナルカラー診断で「ブルーベース」や「イエローベース」という言葉を聞いたことはありますか?
ブルーベースの人は、静脈の影響で肌の色に青みが強く出やすいです。
赤と黄のベースカラーに青を混ぜると、透明感が増し、明るく見える肌色を作ることができます。
色の濃さを調整する際には、白を加えるのではなく、水を加えましょう。
白を使うと明るさは表現できますが、透明感を出すには適していません。
色白の肌を描くには透明感が重要です。
そのため、水を使って調整すると、より美しい肌色を作ることができます。
オレンジと白を混ぜることで
「オレンジ+白=肌色」
上記の原理と同じです。
オレンジの単色がある場合、オレンジと白を混ぜ合わせるだけで、肌色を簡単に作ることができます。
肌色を作る際のポイント
肌色は個人によって様々です。
そこで、肌色を作る際のポイントを解説します。
色を暗くする場合は黒ではなく青を使用
暗めの肌色を作りたい場合は、黒ではなく青を使用してください。
黒は強調されすぎて自然な肌色にならず、こげ茶色に近くなってしまいます。
透明感を出す場合は白の代わりに水で薄める
透き通った白い肌を表現したい場合、白で明度を上げるのではなく、水で薄めると効果的です。
透明水彩絵の具を使用している場合は、水を少なめにして塗ってください。
透明水彩絵の具の場合、白を使わずに水で濃淡を調整するのが基本です。
肌色を作るための重ね塗りの方法

これまで紹介した絵の具の色の作り方は、絵の具を混ぜる「混色」でした。
これは、パレットで複数の絵の具を混ぜて新しい色を作る方法です。
しかし、色を作る方法には他にも「重色」があります。
これは、異なる色を紙の上に次々と重ね塗りすることで色を作り出します。
混色の場合、事前に混ぜた色を紙に塗るため、比較的軽い印象を与えます。一方、重色は一色を塗って乾かし、さらに別の色を重ねて乾かすことを繰り返します。
そのため、重厚でニュアンス豊かな表現が可能です。
重色は、前に塗った色が透けて見えることが必要なため、透明水彩絵の具で効果的です。
不透明な絵の具では、きれいな色が出にくいです。
絵のイメージに応じて、混色と重色を使い分けることが大切です。
重色で肌色を作るにはどうすればいいでしょうか?重色は、肌の立体感をリアルに表現するのに適しています。
そのため、光の当たり方や肌の質感を考慮しながら色を重ねていきます。
1:最も光が当たる部分は紙の白を残すようにします。
2:影になる部分には青や紫を使います。
3:光が当たる部分には黄色を塗りますが、1の部分は残します。
4:血色の良い部分には赤を使います。
5:全体を見ながら、足りない部分に少しずつ色を追加していきます。
この基本的な手順をもとに、影や光の当たり具合、服や周囲の物からの反射光なども考慮しながら色を重ねていきましょう。
色鉛筆で肌の色を表現する方法
色鉛筆を使って肌の色を表現することが可能です。
まず、ベースとして薄く黄色を塗り、その上から軽く赤を重ねます。
色鉛筆では、白や青を使わなくても肌色を再現できます。
顔の輪郭などに影を付けたい場合は、さらに青を重ねると良いでしょう。
上級者向けには、オレンジ、紫、ピンクなどを使って、顔の赤みを細かく表現する方法もあります。
色の比率や塗り方は絵の内容や個々のセンスに依存しますが、初心者には赤と黄色の二色で描く方法をおすすめします。
絵の具や色鉛筆に“肌色”はない
最初に説明したように、絵の具や色鉛筆には、一般的に「肌色」と呼ばれる色は存在しません。
最近では、この色は「うすだいだい」や「ペールオレンジ」と呼ばれることが一般的です。
これは、人種差別的な言葉であるという意識の高まりからです。
2005年頃には、「肌色」という名称の製品は廃止され、代わりに「うすだいだい」という表記が使われるようになりました。
まとめ
今回は、絵の具を使って肌色を作る方法を紹介しました。
肌色は、赤、黄、白の3色を混ぜることで簡単に作ることができます。
他にも、青や茶を加えたり、水を足したりすることで、肌の色味を変えることができます。
紙に色を重ねていく「重色」という手法では、青、黄、赤などを重ねて肌を塗ると、立体的で重厚感のある人物画を描くことができます。
色を作るのが難しいと感じる方は、肌色に近い絵の具を購入するのも一つの方法です。
ペールオレンジやうすだいだい、ジョーンブリヤンなどのカラーが肌色に近いとされています。
自分で描きたい肌の色に合わせて、使い分けてみてくださいね!
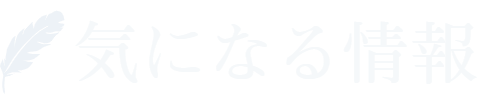



コメント