この記事では、新幹線のトイレについてお話しします。

(出典元:車両のご案内|JR東海)
ネットを見ると新幹線のトイレの位置やランプ、仕組み及び処理方法などに関する検索が多いようです。
そこで、新幹線のトイレについて、これらの疑問にお答えしたいと思います。
新幹線のトイレの位置

※画像はイメージ図です。
新幹線のトイレは、基本的には奇数番号の車両の車端部にあります。
つまり、1、3、5、7、9、11、13、15番車にトイレが設置されています。
1号車では、2号車側の車端にトイレがあります。
同様に、他の奇数号車もこの配置になっています。
トイレの位置を把握しておくと、指定席を予約する際に便利です。
自由席車では、座席数が多い2号車がおすすめですが、トイレが心配なら1号車側の座席を選ぶのが良いです。
グリーン車では、奇数番号の車両にトイレが備えられています。
また、グランクラス(東北新幹線・北海道新幹線の10号車、北陸新幹線・上越新幹線の12号車)には、トイレが完備されています。
のぞみ、ひかり、こだまの新幹線のトイレの位置につて
のぞみ、ひかり、こだまの新幹線のトイレの位置については、いずれも16両編成に統一されており、全列車で同じ配置です。
男女用2カ所と男子小用1カ所が1、3、5、7、9、11、13、15号車などの奇数号車に設けられています。
ただし、山陽新幹線内を走るひかりとこだまは8両編成で、1、3、5、7、9号車にトイレがあります。
新幹線のトイレ案内
新幹線の各車両にはトイレがありますが、その数や設備は車両によって異なります。
以下では、新幹線のトイレ設備について紹介します。
新幹線のトイレの設備
新幹線のトイレは、一部の古い車両を除いてすべて洋式です。
男性専用の小用便器があるトイレもあります。
各列車には1箇所、多機能な大型トイレも設置されています。
男女兼用個室トイレ
洋式便器が備えられた個室です。
おおむね2両に1箇所あり、1箇所につき2つの個室があります。
一部の車両では、暖房付きの自動開閉便座やシャワートイレ機能が備わっています。
個室内には小さな手洗い場もあります。
新幹線のトイレは、1箇所につき、男女兼用と女性専用の個室が1つずつ備わっています。
ただし、東海道新幹線を走る車両には、女性専用の便所はなく、個室便所はすべて男女兼用です。
その他の路線でも、古い車両ではすべて男女共用となる場合があります。
男性小用トイレ
男性向けの小用トイレです。
おおむね2両に1箇所、1つの個室があります。
個室内には小さな手洗い場があります。
多機能トイレ
オストメイトや車いすに対応した大型の多機能トイレです。
自動ドアがあり、内部は広く、おむつ交換台もあります。
1編成につき1箇所のみ設置されています。
それでは、新幹線のトイレのランプについて説明します。
客室内のトイレのあるデッキに面した扉の右上には、トイレを表すピクトグラム(絵文字)があります。
この絵文字はランプとして表示されています。
新幹線のトイレランプの意味と仕組み

新幹線のトイレには、常にランプが設置されています。
このランプには点灯と消灯の2つの状態があります。
ランプが点灯している場合は、トイレが使用中であることを示しています。
一方、ランプが消灯している場合は、トイレが空いていることを意味しています。
ランプは、トイレの個室のカギと連動しており、個室が閉まると点灯します。
ただし、男子小用のトイレはカギがないため、男性が使用する際にはランプが点灯しません。
トイレを利用する際には、必ずランプの状態を確認してください。
新幹線のトイレの種類と仕組み
新幹線のトイレには、主に次の2種類の仕組みがあります。
1:真空吸引式
2:清水空圧式
これらの仕組みについて順番に説明します。
新幹線のトイレの処理:真空吸引方式

真空吸引方式は、汚物タンク内を真空状態にし、空気圧差を利用して排泄物を吸引する仕組みです。
この方式の利点は、最小限の水で排泄物を流すことができることです。
便器の穴が小さい場合は、真空吸引方式であると覚えておいてください。
最新の車両には、この真空吸引方式が採用されているようですね。
真空吸引方式のトイレは、元々は飛行機などの航空産業で使用されていたものを、新幹線用に改良したものです。
以下の新幹線で採用されています。
・東海道新幹線:N700系(のぞみ、ひかり、みずほ、さくら)、700系(ひかり、こだま)、500系(こだま)
・東北新幹線:E2系(やまびこ)、E3系(やまびこ、なすの、つばさ)
・上越新幹線:E2系(とき)
・九州新幹線:N800系(つばめ)
・秋田新幹線:E6系(こまち)
次に、清水空気圧方式です。
新幹線のトイレの処理:清水空気圧方式

清水空気圧方式は、水を噴射して水圧と重力を利用して排泄物をタンクに落とす方式です。
以下の新幹線で採用されています。
・北海道新幹線:E5系・H5系
・東北新幹線:E5系・H5系
・北陸新幹線:E7/W7系(かがやき、はくたか、つるぎ)
・上越新幹線:E5系・W5系
清水空気圧方式は、真空吸引方式よりも多くの水を必要とします。
そのため、最近では清水空気圧方式のトイレは少なくなっています。
新幹線のトイレでは、初代「のぞみ」用車両の300系では清水空気圧方式が使用されていましたが、その後の車両では真空吸引方式が主流となりました。
ただし、現在の最新型車両である北陸・上越新幹線のE5系・W5系と、東北・北海道新幹線のE5系・H5系は、清水空気圧方式に戻っています。
真空吸引方式は停電時に作動しないという弱点があり、このため清水空気圧方式が再評価されているようです。
汚物タンクに貯められた排泄物は、車両基地で抜き取られ、下水道や浄化槽などで処分されます。
そのまま線路に垂れ流されることはありませんので、安心してください。
まとめ
新幹線のトイレに関する情報を紹介しました。
新幹線のトイレの位置は奇数号車にあります。
ランプが点灯しているときは使用中ですが、男子小用の場合はランプが点灯しません。
新幹線のトイレの仕組みは清水空圧式と真空吸引式の2種類がありますが、真空吸引式が主流です。
ただ、東北新幹線などの一部の新幹線では、停電に弱いという理由で最新式の清水空圧式を採用しています。
新幹線のトイレに関心がある方は、この記事を参考にしてください。
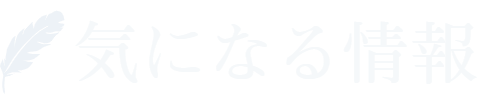




コメント